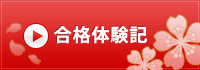現役合格おめでとう!!
2025年 新松戸校 合格体験記

早稲田大学
商学部
全トラック
河野玖人 くん
( 小金高等学校 )
2025年 現役合格
商学部
入学したての時はあまり受験に対して危機感をもっておらず、部活があってあまり勉強時間もとれなかったため、時間がある時もただ淡々と受講などをこなしていただけでした。しかし、模試で全然成績が伸びずに危機感を持ち始めてからは、受講や参考書の復習にしっかりと時間を取って勉強を進めていき、その結果共通テストの過去問の点数をどんどん伸ばすことができました。
そして8月の模試では、自分の中で過去最高の結果を出すことができ、そこから自信がついて早稲田大学の2次私大過去問演習講座にも臆することなく積極的に取り組むことができました。また、9月以降は志望校別単元ジャンル演習講座で自分の苦手な分野を中心にアウトプットしつつ、そこで間違えた問題形式や知識を頭にいれながら勉強を進めていくことで、早稲田大学の過去問にも対応することができる力がどんどんついていきました。受験終盤、共通テストが終わってからは少しやる気が出ないときもありましたが、なんとか踏ん張って最後までやり抜くことができました。
最後まで受験勉強をやり抜くことができたのは東進に通っていた友達と競い合ったり、担任助手の方に励ましてもらったりしたことのおかげだと思っています。時にはモチベーションが上がらなかったり、集中できなかったりすることがあるかもしれないけど、これから受験を迎えるみなさんは東進の友達や担任助手の方などと助け合いながら頑張ってほしいと思います。
そして8月の模試では、自分の中で過去最高の結果を出すことができ、そこから自信がついて早稲田大学の2次私大過去問演習講座にも臆することなく積極的に取り組むことができました。また、9月以降は志望校別単元ジャンル演習講座で自分の苦手な分野を中心にアウトプットしつつ、そこで間違えた問題形式や知識を頭にいれながら勉強を進めていくことで、早稲田大学の過去問にも対応することができる力がどんどんついていきました。受験終盤、共通テストが終わってからは少しやる気が出ないときもありましたが、なんとか踏ん張って最後までやり抜くことができました。
最後まで受験勉強をやり抜くことができたのは東進に通っていた友達と競い合ったり、担任助手の方に励ましてもらったりしたことのおかげだと思っています。時にはモチベーションが上がらなかったり、集中できなかったりすることがあるかもしれないけど、これから受験を迎えるみなさんは東進の友達や担任助手の方などと助け合いながら頑張ってほしいと思います。

早稲田大学
商学部
全トラック
柴田夏芽 くん
( 柏南高等学校 )
2025年 現役合格
商学部
僕は高校1年生の終盤に入学しましたが、本格的に勉強を開始したのは修学旅行の後でした。そのあと3年生になって初めての高校で行われた模試で学年1位を取ることができてとても達成感を感じ、勉強の楽しさを感じることができました。高校3年生の秋では思うように成績が伸びず、悩んだ時期がありましたが目標に向かって毎日努力し続けたので第1志望の大学に合格することができました。僕が大学受験で大切だと感じたことは2つあります。
1つ目は「環境」です。僕は特別進学率が高い高校に通っていたわけではありませんでしたが、東進で学習の意欲が高い仲間と出会うことができていい刺激をもらい、怠ることなく毎日継続して閉館まで校舎に残って長時間勉強し続けることができました。2つ目は「体調管理」です。受験生にとって毎日勉強を継続することは非常に重要なことだと思います。ですが体調を崩してしまうと勉強が中断されて思うように学習を進めることができなくなってしまいます。そのため受験期間は特に体調管理に気を付けていて、具体的には睡眠時間の確保や食事をしっかりとる等、毎日の生活リズムを崩さない心掛けをしていました。
受験で本領を発揮するためには、日ごろからの継続した努力が必要です。毎日全力で取り組み続けることが志望校合格への1番の近道だと思います。これから受験を迎える皆さんは日々の努力を欠かさずに、後悔の残ることの無いように最大限の努力量で頑張ってください。
1つ目は「環境」です。僕は特別進学率が高い高校に通っていたわけではありませんでしたが、東進で学習の意欲が高い仲間と出会うことができていい刺激をもらい、怠ることなく毎日継続して閉館まで校舎に残って長時間勉強し続けることができました。2つ目は「体調管理」です。受験生にとって毎日勉強を継続することは非常に重要なことだと思います。ですが体調を崩してしまうと勉強が中断されて思うように学習を進めることができなくなってしまいます。そのため受験期間は特に体調管理に気を付けていて、具体的には睡眠時間の確保や食事をしっかりとる等、毎日の生活リズムを崩さない心掛けをしていました。
受験で本領を発揮するためには、日ごろからの継続した努力が必要です。毎日全力で取り組み続けることが志望校合格への1番の近道だと思います。これから受験を迎える皆さんは日々の努力を欠かさずに、後悔の残ることの無いように最大限の努力量で頑張ってください。

早稲田大学
文化構想学部
文化構想学科
加藤栞里 さん
( 小金高等学校 )
2025年 現役合格
文化構想学部
私は高2の夏休みから受験勉強を始めました。当時は部活で忙しく、なかなか集中して取り組むことができずにいました。ですが夏休みの終わり頃、周りも次々に受験勉強を開始するようになり、私もそれに奮起されて真剣に勉強に取り組むようになりました。
私は元々現代文が苦手で、勘で解いてしまうことが多かったのですが、現代文の受講で解くプロセスと解答根拠を大切にする姿勢が身につき高1の冬頃には模試で満点を取れることもありました。古典は、受講はとっていたものの、テキストの付録の文法や古典常識の読み込みが甘かったり、単語は多義語も1番重要な意味だけしか覚えていなかったりと、高3の夏まで基礎ができておらず、問題を解くときに対応できませんでした。夏からもう一度基礎をやり直したのですが、他にもっと時間をかけなければならないことがあるなか古典に多くの時間をかけてしまったことは後悔してます。受講を受ける際に基礎を完璧に覚えておくべきでした。
世界史は受講を取らず勉強していました。自分のペースで進められる一方、受講よりも情報量が少なく、かつ耳で聞かないと覚えづらいということもあって始めはなかなか覚えられないことが多かったです。ですが、高3の夏休みに教科書や資料集を読み込んだことで時系列や細かな情報まで覚えることができました。また、情報をアウトプットするために白紙に単語や流れを書き込んでいくという勉強法も良かったと思います。
夏休みまでは志望学部の推薦について一切考えず、一般入試に向けた勉強をしていました。推薦が決まった後も一般受験の人と同じ気持ちで取り組もうと思い、それまでと変わらず勉強をしました。一般の人との学力差を狭め、なおかつ自身の成長にも繋がったので良かったと思います。受験を通して、自身を見つめ直すことが出来ました。生活のだらしなさ、集中力の無さ、メンタルの弱さなど悪いところがいくつも出てきましたが、受験勉強のおかげで多少改善することができたと思います。志望校に合格することをもちろん大切ですが、受験期間を経て人間としてレベルアップしていくことが1番大切なのではないかと思います。
私は元々現代文が苦手で、勘で解いてしまうことが多かったのですが、現代文の受講で解くプロセスと解答根拠を大切にする姿勢が身につき高1の冬頃には模試で満点を取れることもありました。古典は、受講はとっていたものの、テキストの付録の文法や古典常識の読み込みが甘かったり、単語は多義語も1番重要な意味だけしか覚えていなかったりと、高3の夏まで基礎ができておらず、問題を解くときに対応できませんでした。夏からもう一度基礎をやり直したのですが、他にもっと時間をかけなければならないことがあるなか古典に多くの時間をかけてしまったことは後悔してます。受講を受ける際に基礎を完璧に覚えておくべきでした。
世界史は受講を取らず勉強していました。自分のペースで進められる一方、受講よりも情報量が少なく、かつ耳で聞かないと覚えづらいということもあって始めはなかなか覚えられないことが多かったです。ですが、高3の夏休みに教科書や資料集を読み込んだことで時系列や細かな情報まで覚えることができました。また、情報をアウトプットするために白紙に単語や流れを書き込んでいくという勉強法も良かったと思います。
夏休みまでは志望学部の推薦について一切考えず、一般入試に向けた勉強をしていました。推薦が決まった後も一般受験の人と同じ気持ちで取り組もうと思い、それまでと変わらず勉強をしました。一般の人との学力差を狭め、なおかつ自身の成長にも繋がったので良かったと思います。受験を通して、自身を見つめ直すことが出来ました。生活のだらしなさ、集中力の無さ、メンタルの弱さなど悪いところがいくつも出てきましたが、受験勉強のおかげで多少改善することができたと思います。志望校に合格することをもちろん大切ですが、受験期間を経て人間としてレベルアップしていくことが1番大切なのではないかと思います。

早稲田大学
文化構想学部
文化構想学科
松下瑛志 くん
( 小金高等学校 )
2025年 現役合格
文化構想学部
僕は高校1年生の3学期ごろに東進に入学しました。入学理由は、東進が学校の近くにあり、放課後や部活終わりに寄りやすいことや、同じ学校の人が多くいたことでした。最初の頃は勧められた講座をこなしていって基礎を固め、後々苦しまないようにという意識で勉強していました。
高3になり、受験生として本格的に勉強に努める時期になる頃にはある程度基礎が出来上がっていたので、共通テストの過去問や一般入試の過去問もそれほど嫌悪感無く取り組めたかと思いますが、苦手な科目を後回しにしてしまっていたことには悔いが残ります。しかし、勉強のモチベーションを維持するためには、まず勉強をプラスに捉えないとなかなか進まないので、得意な科目や好きな科目を多めに時間を取ることも自分のゴールから逆算して余裕があるのなら悪くはないのかなと思います。自分は早稲田志望で科目数は3教科と比較的負担が少なかったので、多少科目ごとの量のバランスがずれてもどうにかはなりました。ただ、早稲田の入試の特質上、全体的にバランスよく点数を取れる人が受かりやすくはあるので、早稲田を目指す人は、まずとりわけ苦手な科目を無くすことから始めてみると良いと思います。
先ほど逆算について触れましたが、僕の経験を通して一番伝えたいことは、この「逆算」についてです。逆算ができる人とできない人とでは、合格可能性が大きく変わると自分は思っています。たくさんの参考書、情報、コンテンツが溢れている今日、ただただ闇雲に勉強していっては、合格のための実力をつけるのが試験日までに間に合わないなんてことになりかねません。自分の志望校はどのような問題が出て、自分は今どのくらいの実力を持っているかを把握することで、最適とは言わずとも自分が必要な勉強法が見えてくると思います。
僕の例を挙げると、自分が志望していた早慶の学部は、文法事項や英熟語の問題がほぼほぼなかったので、夏からはそれらの勉強を一切せず、代わりに単語の問題のレベルが高かったので、英検1級の単語帳を完璧にしました。以上、受験勉強についてのあれこれを書き連ねましたが、最後に自分を合格に導いてくれるものは、自分はこれだけやったんだから大丈夫だという自信です。試験当日、会場で自信を持って試験に臨めるように、これからも努力を続けていってほしいと思います。頑張ってください!
高3になり、受験生として本格的に勉強に努める時期になる頃にはある程度基礎が出来上がっていたので、共通テストの過去問や一般入試の過去問もそれほど嫌悪感無く取り組めたかと思いますが、苦手な科目を後回しにしてしまっていたことには悔いが残ります。しかし、勉強のモチベーションを維持するためには、まず勉強をプラスに捉えないとなかなか進まないので、得意な科目や好きな科目を多めに時間を取ることも自分のゴールから逆算して余裕があるのなら悪くはないのかなと思います。自分は早稲田志望で科目数は3教科と比較的負担が少なかったので、多少科目ごとの量のバランスがずれてもどうにかはなりました。ただ、早稲田の入試の特質上、全体的にバランスよく点数を取れる人が受かりやすくはあるので、早稲田を目指す人は、まずとりわけ苦手な科目を無くすことから始めてみると良いと思います。
先ほど逆算について触れましたが、僕の経験を通して一番伝えたいことは、この「逆算」についてです。逆算ができる人とできない人とでは、合格可能性が大きく変わると自分は思っています。たくさんの参考書、情報、コンテンツが溢れている今日、ただただ闇雲に勉強していっては、合格のための実力をつけるのが試験日までに間に合わないなんてことになりかねません。自分の志望校はどのような問題が出て、自分は今どのくらいの実力を持っているかを把握することで、最適とは言わずとも自分が必要な勉強法が見えてくると思います。
僕の例を挙げると、自分が志望していた早慶の学部は、文法事項や英熟語の問題がほぼほぼなかったので、夏からはそれらの勉強を一切せず、代わりに単語の問題のレベルが高かったので、英検1級の単語帳を完璧にしました。以上、受験勉強についてのあれこれを書き連ねましたが、最後に自分を合格に導いてくれるものは、自分はこれだけやったんだから大丈夫だという自信です。試験当日、会場で自信を持って試験に臨めるように、これからも努力を続けていってほしいと思います。頑張ってください!

慶應義塾大学
経済学部
経済学科
大塲圭祐 くん
( 小金高等学校 )
2025年 現役合格
経済学部
僕が慶應義塾大学を志望したきっかけは、早稲田大学と並んで私立文系最難関の大学であり、昔から憧れを持っていたからです。僕は、高校2年生の夏休みに東進に入学した頃、到底早慶を目指せるような学力ではなかったのですが、夢は大きくという理念のもとに、慶應合格という大きな目標を掲げていました。しかし、これが功を奏し、目標として慶應を掲げているうちに、本気で慶應を目指すようになり、勉強量も増えて成績もぐんぐん伸び、結果として、慶應義塾大学から合格を頂くことができました。
次に、具体的な勉強法についてですが、英語はとにかく単語、文法といった基礎を固めた上で高3の夏頃から本格的に長文の参考書を始め、それからは、基礎の復習を続けつつも、様々なテーマに触れて長文の解き方を実践を通して学ぶため、毎日1題は長文を必ず解くようにしていました。国語は高3の夏休みまでに古文単語、文法を固めた上で、夏休み中は基本事項の抜けを確認しつつ、実践を通して知識の応用の仕方を学ぶため、現代文、古文、漢文を毎日1題ずつ解くようにしました。この期間を通して国語の点数は安定させることが出来たため、夏以降は英語、日本史に多くの時間を割くことができました。日本史は常に一問一答と教科書をひたすらに何周も回していました。
また、珍しいかもしれませんが、僕は受験期を通して勉強を辛いと思ったことがあまりありませんでした。これは、友人の存在があったからです。時にはライバルとして、時には仲間として、競い合い、支え合い、切磋琢磨することで、勉強自体を楽しむことができました。勉強を楽しむことができたから、最後まで努力し続けることができたのです。僕が合格出来たのは半分友人のお陰と言っても過言ではありません。それほどにまで友人の存在は大きいものでした。 「受験は団体戦」という言葉はよくばかにされていますが、僕は本当にその通りだと思います。仲間の存在が最後まで僕を支え続けてくれました。夢も努力も苦悩も1人で抱え込まず、仲間と共有していくことが合格への近道だと僕は思います。大きな目標を掲げ、その目標に向かって仲間と共に努力を続け、合格を勝ち取ってください!
次に、具体的な勉強法についてですが、英語はとにかく単語、文法といった基礎を固めた上で高3の夏頃から本格的に長文の参考書を始め、それからは、基礎の復習を続けつつも、様々なテーマに触れて長文の解き方を実践を通して学ぶため、毎日1題は長文を必ず解くようにしていました。国語は高3の夏休みまでに古文単語、文法を固めた上で、夏休み中は基本事項の抜けを確認しつつ、実践を通して知識の応用の仕方を学ぶため、現代文、古文、漢文を毎日1題ずつ解くようにしました。この期間を通して国語の点数は安定させることが出来たため、夏以降は英語、日本史に多くの時間を割くことができました。日本史は常に一問一答と教科書をひたすらに何周も回していました。
また、珍しいかもしれませんが、僕は受験期を通して勉強を辛いと思ったことがあまりありませんでした。これは、友人の存在があったからです。時にはライバルとして、時には仲間として、競い合い、支え合い、切磋琢磨することで、勉強自体を楽しむことができました。勉強を楽しむことができたから、最後まで努力し続けることができたのです。僕が合格出来たのは半分友人のお陰と言っても過言ではありません。それほどにまで友人の存在は大きいものでした。 「受験は団体戦」という言葉はよくばかにされていますが、僕は本当にその通りだと思います。仲間の存在が最後まで僕を支え続けてくれました。夢も努力も苦悩も1人で抱え込まず、仲間と共有していくことが合格への近道だと僕は思います。大きな目標を掲げ、その目標に向かって仲間と共に努力を続け、合格を勝ち取ってください!